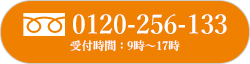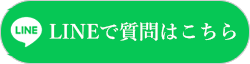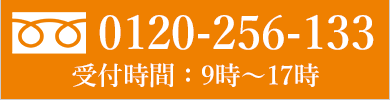永代供養のお墓参りの仕方は?お供えなどのマナーを解説

近年、少子高齢化や核家族化の影響により、「永代供養」を選ぶ方が増えています。お墓の管理や供養を寺院や霊園に任せられるため、子どもや親族に負担をかけたくないという想いから選ばれるケースが多くなっています。
しかし、永代供養を選ぶ際には一般墓の違いを理解しておくことが重要です。理解不足によってトラブルが起きることも稀にあります。
今回の記事では、「永代供養墓のお墓参り」をテーマに、一般墓との違いはあるのかをはじめ、形式別のお墓参りの仕方、注意点などを解説します。
永代供養のお墓参りは一般墓と違う?
一般墓のお墓参りは、墓所に到着したら合掌して一礼し、墓前の掃除を行います。その後、花を供え、必要に応じてお水やお供え物を置き、お線香をあげて手を合わせて故人を偲びます。
「永代供養墓では、お墓参りの方法が特殊なのでは?」と不安に感じる方もいるかもしれませんが、基本的なお墓参りの流れは一般墓とほとんど変わりません。
ただし、永代供養墓には個人墓や合祀墓、納骨堂、樹木葬など様々な形式があり、施設によってルールも異なる点には注意が必要です。
永代供養墓のお墓参りの仕方

ここでは、代表的な3つのタイプ「個人墓・合祀墓」「納骨堂」「樹木葬」ごとに、お参りの仕方や注意点を解説します。
個人墓・合祀墓
一般墓と似た形式で、故人ごとに区画が用意されている個人墓は、通常のお墓参りとほぼ同様の方法で参拝が可能です。花立てや香炉が設置されていることが多く、献花・お線香・お供えをして手を合わせる流れとなります。
一方、合祀墓は他の方と共に埋葬されているため、個別の墓標がないのが一般的です。参拝の際は共同の祭壇や供養塔の前で手を合わせるスタイルになります。
なお、個人墓も永代にわたって個別に管理されるわけではなく、多くの場合は一定期間を経過すると合祀されるのが基本です。合祀後は、個別のお参りはできなくなり、共同の供養塔などで手を合わせる形に変わります。
納骨堂
遺骨を屋内施設で安置するタイプの永代供養墓で、天候に左右されず快適にお参りできるのが大きな特徴です。参拝の際は、まず受付で名前やカードを提示して、故人の納骨スペースを開閉してもらうスタイルが一般的です。自動搬送式やロッカー式など、施設によってシステムは異なります。
屋内という特性上、お線香やろうそくの使用が制限されているケースも多く、代わりに電気式の焼香台が設置されていることもあります。また、生花や食べ物などのお供え物も持ち込みが禁止されている場合もあります。
樹木葬
墓石の代わりに樹木や草花を墓標としており、自然と共に眠ることをコンセプトとした供養形式です。樹木葬にも個別区画タイプや、合祀形式で複数人を埋葬するタイプがあります。墓石の代わりに樹木や草花を墓標としているため、お墓参りで手を合わせる場所は樹の下や指定されたプレートの前になります。
お参りの際は、墓標となる樹木やプレートの前で静かに手を合わせ、故人を偲びます。霊園や施設によっては自然環境や安全面への配慮から、お線香や供物の持ち込みを制限している場合があります。
永代供養墓のお墓参りに関する注意点

永代供養墓を訪れる際は、霊園や寺院ごとのルールにしっかりと従うことが何より重要です。施設ごとにお墓参りの方法やマナーに細かな規定が設けられている場合が多いです。献花やお供え物の種類に制限があったり、お線香の使用が禁止されていたりすることもあるため、事前に確認しておくことが不可欠です。
訪問前には、霊園の公式サイトを確認したり、管理事務所へ直接問い合わせて、開園時間・持ち込み可能なもの・参拝方法などを把握しておきましょう。ルールを知らずに訪れると、供え物が禁止されている場所に食べ物を持ち込んでしまったり、閉園後に足を運んでしまうといったトラブルにもつながります。
また、永代供養墓のお墓参りに限ったことではありませんが、自然環境や他の利用者への配慮も大切です。ごみの持ち帰りや大きな音を立てる行動をしないなど、細かなマナーも意識することが大切です。周囲の人や施設への配慮を忘れず、故人を静かに偲ぶ心を大切にしましょう。
永代供養のお墓参りについて
永代供養のお墓参りは、基本的な作法は一般墓と大きく変わりませんが、各施設ごとにルールが定められており、供養の形式によっても違いがあります。献花やお供え物の可否、お線香の使用などは事前に確認し、ルール・マナーを守って故人を偲ぶことが大切です。
なお、東京都内で樹木葬をご検討中の方には、浅草にある名刹「桃林寺」のガーデニング樹木葬がおすすめです。四季の草花が彩る庭園の中で、自然に包まれたやさしい供養ができるのは、桃林寺ならではの魅力です。新しい供養のかたちとして、多くの方々に選ばれています。
開園時間は9時から17時までで、自然との調和を大切にしているため、献花やお供え物、お線香の持ち込みはご遠慮いただいております。
その代わりとして、手作りの折り紙の花を供える「花手水(はなちょうず)」をご用意しており、訪れる方が静かに故人を偲ぶ時間を過ごせる環境が整っています。